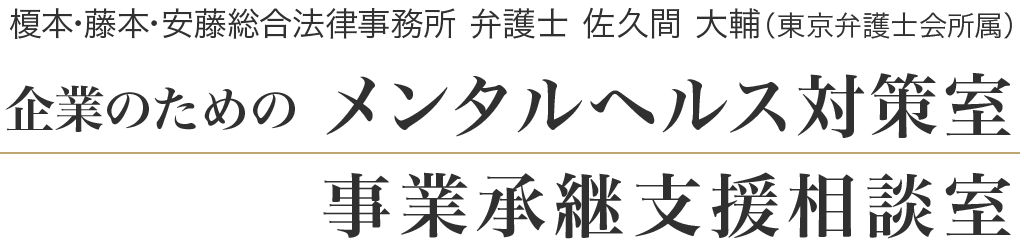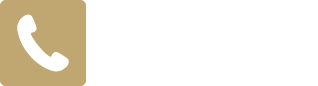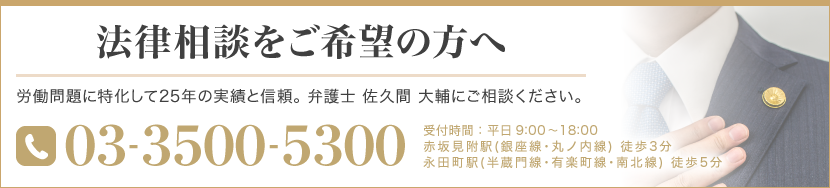就業時間中によく居眠りをする労働者がおり、以前に配置転換(異動)をして社外の者と接触しないようにし、病気であれば治すように指示したのに、その後病院に行かないので、居眠りが改善されない場合、懲戒処分を課すことはできるでしょうか。
労働者は労働契約に基づき労務提供義務を負うのであり、労働契約により定められた内容の労務を提供する健康を保持しなければなりません。健康な心身を保持して労務を提供することが労働契約から求められますので、健康な心身を保持できず、労働契約に定められた労務を提供できなければ、債務の本旨に従った履行の提供をしたことにはならず、減給、解雇、損害賠償という不利益を負う場合があります。その債務不履行が具体的に企業秩序を乱すものであれば、懲戒処分が課されることもあります。
当該労働者の病気が不眠症や睡眠時無呼吸症候群などであれば、治療は可能です。そこで、人事労務担当者は、当該労働者の疾病名や程度、また業務に与える影響を調査・把握した上で、専門外来を受診するなど持病の治療を勧める、持病の症状が重く、所定労働時間中に居眠りをするおそれがあるときは年次有給休暇を取得させるなどして、所定労働時間中に居眠りをしない体調を維持するようにさせてください。
当該労働者が持病の治療に応じず、居眠りが改善しない場合、使用者が就業規則において受診に関して合理的な内容の規定を定めていれば、受診命令を発令することができます。このことは最高裁判決でも認められているのですが、最高裁判決は決して使用者の受診命令の裁量を広範に認めたわけではなく、労働者の健康の早期回復という目的に照らし合理性ないし相当性を肯定し得る内容の指示であることを要すると判断しており、使用者の受診命令には合理性という限定が加えられている点に留意してください。
受診命令が合理的な理由と相当な方法であると認められる場合、例えば、使用者が労働者の傷病の診断や治療、回復を目的としたものであり、その目的に照らして、受診する医療機関、受診の内容・方法や受診時期の指定が相当であるときは、使用者の受診命令が有効となり、労働者の受診義務が発生します。
就業中の居眠りについて上司や人事労務担当者から注意、指導されていたのに持病を受診せず、また受診命令に応じなかったという場合には、当該社員に懲戒処分を課すことができます。
傷病と人事対応に関するその他のQ&A
- メンタルヘルス不調時の相談対応
- 病気を職場に知られたくない労働者への対応
- 病気社員を軽易な業務に就かせた場合の処遇は
- 病気社員の業績評価・能力評価の公平性を担保するには
- 病者の就業禁止-心臓病の労働者が就労継続を希望したら
- 休職中の状況把握-定期的な報告・面接
- 残業禁止の診断に上司や社員が従わない場合の対処
- 病気休職中の私用(運転免許取得)を懲戒できるか
- 職場復帰の可否の判断と職場復帰支援プランの作成
- 受動喫煙を嫌悪する労働者からの配置転換(異動)の希望
- 就業中の居眠りを繰り返す病気社員に受診命令や懲戒処分を課すことはできるか
- 就業中の居眠りを繰り返す病気社員に休職命令、異動命令、懲戒処分を課すことはできるか
- 休職の診断書が提出されない場合は退職扱いにできるか
- 「偽装うつ」が疑われる場合は解雇できるか
- 採用面接でうつ病について聞くことはできるか
- 雇入れ時の健康診断結果により採用内定取消しはできるか