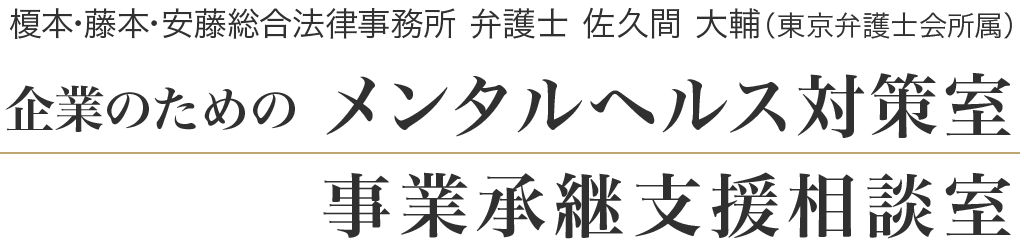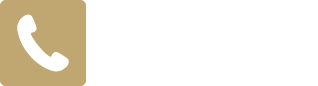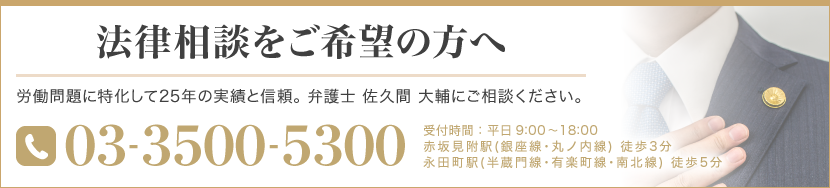過労死等防止対策推進法は、過労死(脳血管疾患・心臓疾患、精神障害・自殺)の防止のための対策を推進し、もって過労死がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的としています。
調査研究を行うことにより過労死に関する実態を明らかにし、その成果を過労死の効果的な防止のための取組に生かすこと、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、これに対する国民の関心と理解を深めること等を基本理念とし、過労死防止対策について、国、地方公共団体、事業主等関係者の相互の密接な連携の下に行われなければなりません。
政府は、毎年、国会に、我が国における過労死の概要および政府が過労死の防止のために講じた施策の状況に関する報告書を提出すること、過労死防止対策を効果的に推進するため、過労死等の防止のための対策に関する大綱を定めることが義務づけられました。
今後、国は、①過労死に関する実態の調査、過労死の効果的な防止に関する研究その他の調査研究、過労死に関する情報の収集、整理、分析および提供を行うこと、②教育活動、広報活動等を通じて、国民の関心と理解を深めるよう必要な施策を講ずること、③過労死のおそれがある者に早期に対応し、過労死等を防止するための適切な対処を行う相談体制の整備および充実に必要な施策を講ずること、④民間の団体が行う過労死の防止に関する活動を支援するために必要な施策を講ずることを実施していくことになります。
そして、事業主は、国および地方公共団体が実施する過労死防止対策に協力するよう努めなければなりません。
過労死等防止対策推進法は、まず、過労死の防止のための対策を効果的に推進する責務を有する国が調査研究、啓発、相談体制の整備等を実施していこうというものであり、いわゆる「啓蒙法」であるから、過労死防止対策に協力する努力義務以外、事業主が直ちに何らかの法的義務を負うわけではありません。
しかし、既に過労死等防止対策大綱が閣議決定されており、今後、国の調査研究が進行したとき、人事労務管理スタッフが座して傍観しているわけにはいきません。その理由として、国の啓発活動や相談活動が奏功すれば、知識を得た労働者や遺族が訴えを起こし、紛争が増加する可能性があることです。それにもかかわらず、人事労務管理スタッフは、労働時間や安全衛生に関する法令や行政通達、健康障害に関する医学知見を知り得るのに、知らないといっても事業主を免責させることにはならないからです。
裁判例においては、人事管理部部長が「残業時間が1か月当たり100時間を超えると過労死の危険性が高くなり、精神疾患の発症も早まるとの知見や、時間外労働を1か月当たり45時間以下にするよう求める厚生労働省の通達等の存在を認識して」いたと認定され、自殺した従業員の遺族から訴えられた事業主の損害賠償責任が認められたものがあります。法令の不知が企業の予見可能性を否定させることにはつながりません。
とすれば、メンタルヘルス対策や過重労働対策に消極的な事業主には「ブラック企業」の烙印を押されかねません。
しかも、過労死等防止対策推進法は、「国民は、過労死等を防止することの重要性を自覚し、これに対する関心と理解を深めるよう努めるものとする」とも規定しており、これ自体は国民の努力義務にすぎませんが、この条文を背景に過労死防止に関心と理解の低い経営者は個人責任を問われかねないといえます。
メンタルヘルス対策・過労死防止に関するその他のQ&A
- 職場のメンタルヘルスケア-うつ病の予防・早期発見
- 組織全体でのメンタルヘルス対策の立案と継続的実施
- 事業場におけるメンタルヘルスケアの進め方
- 従業員のメンタルヘルスに関する日常的な相談活動
- 従業員のメンタルヘルス不調を予防するための人事対応
- 従業員の問題行動に対する人事労務担当者の対応
- メンタルヘルス対策における衛生管理者の役割
- 長時間労働防止とメンタルヘルスケアのための職場環境改善
- メンタルヘルス不調に関する職場復帰支援プログラム
- 過労死等防止対策推進法と企業の損害賠償責任
- 脳・心臓疾患の労災認定基準と使用者の安全配慮義務の履行
- 障害者雇用促進法における差別的取扱いの禁止、合理的配慮措置
- 高血圧のシステムエンジニアが脳出血で死亡したら使用者は安全配慮義務により損害賠償責任を負うか
- 病気社員への業務負担の増加と病状悪化の責任は
- 職場環境を整備する義務は